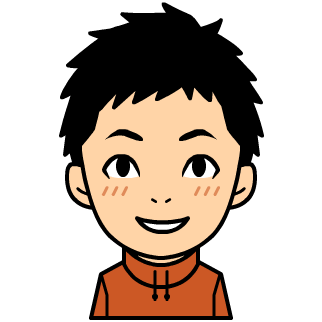もくじ
「え、バブル世代がもう年金もらうの?」
SNSやニュースで見かけたこの話題に、思わず二度見した人も多いのではないでしょうか。
「ついこの間まで、バリバリ働く現役世代だったのに?」
「え、あのバブル組が、もう老後ってこと?」
そう感じたあなたも、きっと“あの頃”をリアルタイムで見てきた世代。
いつの間にか、自分より少し上の世代が年金受給に差しかかっているという事実に、驚きと時代の流れを強く感じずにはいられません。
そもそも「バブル世代」とは?
いわゆる「バブル世代」は、1980年代後半から1990年代初頭に社会人デビューした人たちを指します。
-
就職氷河期?そんな言葉は存在しなかった
-
「売り手市場」が当然
-
就職先を「選べる時代」
-
入社すれば「終身雇用」「年功序列」は約束されたもの
しかも、
-
ボーナスは年2回が当たり前
-
海外旅行は“ご褒美”ではなく“娯楽”
-
ゴルフセットを買い、ブランドバッグを持ち、六本木で夜遊び
まさにバブル景気の波に乗った「華やかな社会人デビュー」がこの世代のイメージでした。
そんなバブル世代が、いま年金受給の年齢に
驚くべきことに、1961〜1964年生まれの人たちは、
2024〜2029年の間に年金受給を開始する年齢(65歳)に到達します。
「え、あの人もう退職したの?」
「ついこの前まで部長だったよね?」
……そんな会話も、日常的になってきました。
“若手”だったはずのバブル組が、もう老後の入口に立っているという現実。
時間の流れの速さに、思わずため息が出てしまいます。
平均寿命も定年も、変わった
さらに言えば、平均寿命は延び、定年年齢も65歳・70歳へと延長されています。
「55歳で退職して悠々自適」なんてのは、すでに遠い過去の話。
-
今のシニアは元気だし、まだまだ働いている
-
定年後の再雇用や、シニア起業も当たり前になった
-
「人生100年時代」という言葉が現実味を帯びている
そんな時代に、「バブル世代の年金開始」は、ある種の節目として社会に静かに、けれど確実なインパクトを与えています。
「あの時代」と「今」のギャップがすごい
あの頃の常識は、今やすっかり時代遅れに。
| 昔(バブル時代) | 今 |
|---|---|
| 年功序列が基本 | 成果主義が当たり前 |
| 終身雇用が保障されていた | 転職・副業が一般的 |
| ボーナスで家電を一括購入 | 物価高騰で節約が日常 |
| 銀行に預ければ利子がついた | 金利ゼロで資産形成に悩む |
「あの頃は良かった」と思うのは当然かもしれません。
でもそれと同時に、現代の不確実さの中で生きる若い世代の苦労も、見えてくる気がします。
バブル世代=勝ち組? 実際には「揺れる世代」でもある
華やかな時代に社会人になったとはいえ、バブル世代はずっと順風満帆だったわけではありません。
-
バブル崩壊により、多くの企業が業績悪化
-
リストラの波に巻き込まれた人も
-
転職・再就職を経験した人も少なくない
-
IT化・グローバル化・成果主義への対応に苦労した声も多い
また、現在は
-
親の介護
-
子どもの進学・就職
-
持ち家のローン返済
-
体力の衰えと健康不安
など、人生の“負担期”のピークを迎えている人も多いはずです。
そんな中で、いよいよ「年金受給」という言葉が現実のものになってくると……
「自分はもうそんな歳なのか」と複雑な気持ちになるのも当然です。
時代の変化を実感する「驚きと感慨」
街中で見かけるシニア層が、かつての「先輩」「上司」だった世代。
テレビに出ている著名人たちが、次々とリタイア宣言をしていく。
「自分が若手だった時代」の記憶は、まだはっきりとあるのに。
でもその感覚とは裏腹に、確実に時代は流れている。
そして自分自身も、確実に“次のフェーズ”へと進んでいる――。
そんな実感を、バブル世代の年金受給開始というニュースは、静かに、しかし力強く突きつけてくるのです。
まとめ:ひとつの時代が終わり、また新しい時代へ
バブル世代が年金を受け取り始める。
それは、単なる「年齢の節目」ではなく、社会全体の大きな移り変わりの象徴とも言えるでしょう。
あの頃、キラキラと輝いていた人たちが今、穏やかにセカンドライフに入ろうとしている。
そして私たちもまた、その背中を見ながら、確実に“次の世代”に移っていく。
-
バブルの熱気
-
景気の浮き沈み
-
社会構造の変化
-
家族や仕事のかたちの移り変わり
それらすべてを通して、今の自分がある――
そう思うと、時代の流れが、なんとも言えない重みを持って感じられるのではないでしょうか。