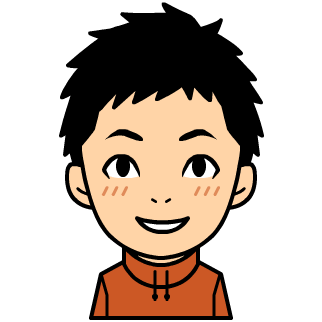もくじ
氷河期世代は「年金制度の谷間」にいると言われる理由
就職氷河期を経験した世代、つまり現在40〜50代の方々は、バブル崩壊後の不況の中で社会に出て、正社員になれず非正規やフリーターとして長く働かざるを得なかったという背景を持っています。
その結果、年金制度の恩恵を受けにくい立場に置かれてきたとも言われています。
「将来、自分はどれくらい年金をもらえるのか?」
「年金だけで暮らせるとは思えないけど、どう補えばいいの?」
こうした不安は、氷河期世代にとって切実な問題です。この記事では、「なぜ年金が少なくなりやすいのか?」その原因を整理しつつ、今からできる現実的な対策について、わかりやすく解説していきます。
なぜ氷河期世代の年金が少なくなりやすいのか?
年金が少ない理由には、氷河期世代特有の社会的背景があります。
● 非正規雇用や失業期間が長かった
多くの人が新卒時に正社員になれず、非正規やアルバイトで生計を立てていた時期が長く続きました。
非正規雇用では、厚生年金に加入できないケースも多く、将来の年金額に大きく響いているのです。
● 保険料の未納・未加入がある人も
経済的な余裕がなく、国民年金の保険料を払えなかった、または「どうせもらえないから払わない」と未加入だったという声も聞きます。
ですが、これも将来の年金額を大きく減らす原因になります。
● 収入が低く、納付額も少ない
厚生年金は「収入に応じて」将来の年金額が決まります。つまり、給与が低いほど納める保険料も少なくなり、その分、受取額も少なくなるという構造です。
年金制度の仕組みを簡単におさらい
年金についての不安を解消する第一歩は、「仕組みを知ること」です。
● 国民年金と厚生年金の違い
-
国民年金(基礎年金):20歳以上60歳未満の全国民が対象。主に自営業者やフリーランスが加入。
-
厚生年金:会社員や公務員など、給与所得者が加入。国民年金に上乗せされる形で、受取額が増える。
● 支給開始年齢と満額受給の条件
-
年金の受給開始年齢は原則65歳。
-
国民年金を40年間(480ヶ月)納付していれば、満額(令和6年度時点で約月6万8,000円)受け取れます。
納付期間が短いと、当然もらえる金額も減ってしまいます。
● 自分の年金額を調べるには?
「ねんきんネット」という日本年金機構のサービスを使えば、過去の納付履歴や将来の見込み額を確認できます。
まずは現状を「見える化」して、足りない部分をどう補うかを考えることが大切です。
将来への不安にどう備えるか?現実的な対策
年金だけでは不安…でも今からでもできる備えがあります。
● iDeCo(イデコ)の活用
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、自分で年金を作る制度です。
毎月の掛金を運用し、60歳以降に一時金や年金として受け取ることができます。
-
掛金は全額所得控除の対象となり、節税メリットあり
-
運用益も非課税
-
少額から始められ、自分のペースで積み立て可能
iDeCoは「第2の年金」として、年金の不足分を補う手段として非常に有効です。
● つみたてNISAなどの積立投資
年金以外での資産形成には、つみたてNISAの活用もおすすめです。
こちらも運用益が非課税で、少額からコツコツ積み立てられる仕組みです。
長期・分散・積立という投資の基本を押さえれば、リスクを抑えて資産を育てることができます。
● 65歳以降も働くという選択肢
年金の支給開始を遅らせると、その分受給額が増える「繰下げ受給」という仕組みもあります。
また、健康であれば70歳まで働くことで、年金額や生活資金を増やすことも可能です。最近では高齢者向けの就労支援や求人も増えており、「長く働く」ことが現実的な選択肢になっています。
● 支出の見直しと老後生活設計
年金を補うには、「生活費をどう減らすか」も重要です。
-
固定費の見直し(通信費、保険料など)
-
コンパクトな住まいへの転居
-
自炊や生活スタイルの工夫
収入を増やすだけでなく、支出を見直すことで生活の安定感が増します。
社会的支援制度の活用
必要に応じて、社会保障や支援制度に頼ることも“自立”の一部です。
● 最低限の生活を支える制度
-
生活保護:生活が困難な場合の最終的な支援制度
-
老齢基礎年金の最低保障:納付期間が足りない人も、一定条件で受給可能
-
住宅支援制度:家賃補助や公営住宅の利用など
こうした制度があることを知っておくことで、不安の“底抜け”を防ぐことができます。
● 地域や民間のサポート
-
高齢者向けの無料相談窓口(自治体や社協)
-
シルバー人材センターなど、働く意欲を支える組織
-
食品や衣類などの支援を行う地域のNPO団体
社会全体での支援体制も広がってきています。頼れるものは遠慮なく使いましょう。
まとめ
氷河期世代が抱える年金の問題は、決して個人の努力不足ではありません。
時代の影響と構造的な要因によるものであり、社会全体が向き合うべき課題です。
とはいえ、将来の不安を少しでも減らすためには、自分でできる備えを一つずつ積み上げていくしかありません。
-
制度を知ること
-
少額でも貯めること
-
働く道を残すこと
-
支出を見直すこと
どれも大きな一歩です。完璧な老後ではなく、「安心して生きられる老後」を目指すことが大切です。
「もう遅い」ではなく、「今からでも遅くない」
今この瞬間から、あなたの未来の準備は始められます。