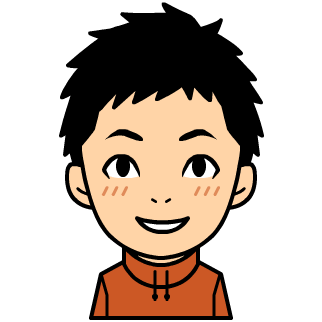「最近、物価が高すぎる…」「デフレ時代のほうが良かったのでは?」
そんなふうに思ったことはありませんか?
確かに、デフレの時代は「物が安い」というメリットがありました。しかし、「安い=良い」と単純に考えるのは危険です。デフレには、給料が上がらない、企業が成長しない、経済が停滞するといった深刻なデメリットがありました。
この記事では、「デフレ時代に戻れば全て解決する」という考えが本当に正しいのか?を検証し、デフレの本当の姿をわかりやすく解説していきます。
もくじ
デフレとは何か?なぜデフレが起きるのか?
まず、「デフレって何?」という基本を押さえておきましょう。
デフレ(デフレーション)とは?
👉 物価が継続的に下がり続ける現象のこと。
物の値段が下がるのは一見いいことのように思えますが、実は経済全体にとっては大きな問題を引き起こします。
デフレが起きる仕組み
1️⃣ 企業の売上が減る
2️⃣ 給料を上げる余裕がなくなる(むしろカットされる)
3️⃣ 収入が増えないので、消費者が買い控えをする
4️⃣ さらに物価が下がる → 悪循環が続く
こうして経済全体が縮小し、長期的に国全体の活力を奪ってしまうのがデフレの怖いところです。
デフレのメリット(表面的な良さ)
確かに、デフレには「一見すると良い部分」もあります。
✔ 物価が安くなる → 生活費を抑えられる
✔ 消費者にとっては買い物しやすい → 価格競争が激しくなり、より安い商品が増える
「給料が上がらなくても、物価が安ければ問題ないのでは?」と思うかもしれません。
でも、本当にそうでしょうか?
デフレの本当のデメリットとは?
① 給料が上がらない(むしろ下がる)
企業の売上が下がると、「人件費を削ろう」「昇給は無理」となります。その結果、給料が上がらないまま物価だけが下がる状態に。
💡 「デフレの時代は物が安かった」と言うけど、給料も安かったのを忘れていませんか?
② 経済が停滞し、企業が投資しなくなる
物価が下がり続けると、企業は儲かりません。そうなると、設備投資や新規事業を控えるようになり、新しい産業が生まれにくくなります。
👉 「デフレ時代は新しいビジネスがなかなか生まれなかった」のは、こうした背景があったからです。
③ 就職氷河期を生み出したデフレ
デフレ期には、企業は採用を控えるようになります。
特に1990年代後半〜2000年代初頭のデフレ期では、企業が新卒採用を大幅に縮小しました。その結果、「就職氷河期世代」と呼ばれる人たちが生まれ、キャリア形成に大きな影響を受けました。
💡 「物が安かった時代=働き口が少なかった時代」でもあるんです。
④ 企業の倒産が増え、雇用が不安定になる
デフレになると、企業同士の価格競争が激化し、利益を出せない企業が次々に倒産します。
特に中小企業は、価格を下げ続けることで利益がほとんど出せなくなり、倒産に追い込まれました。
「デフレ=会社が潰れやすい時代」だったことも忘れてはいけません。
デフレが続いたことで日本経済に起きた問題
デフレが長引いたことで、日本経済にはこんな影響が出ました。
📉 企業の賃金抑制 → 給料が増えず、生活が苦しくなる
📉 社会保障費の増大 → 高齢化社会が進み、税負担が増える
📉 国際競争力の低下 → 海外に比べて成長率が鈍化
「物が安いからデフレのほうが良い」というのは、あくまで一時的なメリットにすぎません。長期的に見れば、デフレは国全体の成長を止めてしまうのです。
デフレとインフレ、どちらがマシなのか?
「じゃあ、今のインフレは良いことなの?」と思うかもしれません。
もちろん、急激なインフレは生活に負担をかけるので、一概に「インフレのほうが良い」とは言えません。しかし、デフレが続くと経済がどんどん縮小し、給料も上がらなくなるというのは歴史が証明しています。
「適度なインフレ」が理想
✔ 物価が2%程度上がる(企業が適正な利益を確保できる)
✔ 給料も一緒に上がる(労働者の収入が増える)
✔ 企業が投資をしやすくなる(新しい産業が生まれる)
このようなバランスの取れた状態が、「健全な経済成長」に必要なのです。
おわりに:デフレが良かったと思う前に、もう一度考えよう
「デフレが良かった」と言う人は、「物が安かった」という部分だけを見ていることが多いです。
しかし、デフレの時代は…
❌ 給料が上がらない
❌ 企業が成長しない
❌ 就職氷河期で若者の雇用が厳しくなる
❌ 企業の倒産が相次ぎ、不景気が続く
こんな時代だったことを忘れてはいけません。
💡 大切なのは「物価を下げること」ではなく、「給料が上がる環境を作ること」!
私たちが目指すべきは、「適度なインフレの中で、給料も上がる」経済です。
デフレの罠にハマらないように、今一度、考えてみましょう!